ブラひも,あるいは自己と非自己の境界について
今回はとても難解な哲学的テーマを扱いたい。敷居が高いかもしれないので苦手な方は読み飛ばしていただきたい。
さて今日の最初の話題は「ブラひも」である。「ブラひも」とは何だろうか。それは,「ブラ(ジャー)」の「(肩)ひも」である。
このわかりやすい,明晰判明な事実が,フランスではえてして忘れられがちである。ここフランスでは,それはむしろ,ほとんど空気のような存在なのだ。そしてその事実自体がわれわれを当惑させる。
灼けつく太陽,急な夏の到来。スプリングコートを脱いだ女たちが,濃いサングラスとともに次に身に纏うのは,できるだけ肌を出せるタンクトップやキャミソールである。もちろん,ヒップハガーのジーンズとのあいだに覗くのは,白いまたは黒い下腹部だ。いろいろな理由があるが,老若を問わず,またスタイルを問わず,稚内(わっかない)よりはるか北に位置するパリの女性たちは,こよなく太陽を好むのだった。
日本でも女性の「ヘソ出しルック」(何か古い言い方のような――なぜか「ホンダミナコ」という名前が連想される――まあそういう世代ではある)は流行っていると聞く。しかし,全体としてのこちらのような眺めは,日本では決して見られないだろうとぼんやり思う。それはいったいなぜなのか?
▼ひとことで言うと,思うに,彼女らは日本人とは「皮膚感覚が違う」からである。ここで言う「皮膚感覚」とは,自己の境界の感覚という意味である。すなわち,大雑把な言い方をすれば,「皮膚」の内側は「自分」であり,「皮膚」の外側は「自分でないもの」である。逆に,自己と非自己の境界線を,さしあたり,体表面に位置する「皮膚」と呼ぶわけである。
その感覚が「違う」というのはどういう意味か。それは,「見せていい場所」と「見せてはいけない場所」との区別のしかたが違う,ということだ。フランス(おそらくヨーロッパ全域)の場合,日本と異なり,「ブラひも」は「見せていい場所」に分類される。したがって多くの女性はブラの上に直接キャミソールを着用しており,そのため肩ひもはたいてい左右にわたり4本が観察可能である。もっとも肩ひもが2本しか観察できない人々も存在し,そうした人々のたわわな2つのふくらみの山頂には,小さな突起がそれぞれ確認できる(書いてて恥ずかしい)。
われわれ男子としては,パリに暮らすかぎり,「セクシーに非ずんば女に非ず」とでも言わんばかりのパリズィエンヌたちのこうした開放的な身なりに,あくまで確率論的にではあれ,目のやり場に困る事態を早晩迎えることとなる。しかししばらく見ていると(あんまり見るなよ。でも見てても別にヘンではない,向こうにしても「見せていいところ」だから),何かヘンだな,と思えてくる。例えば上の服と全く色の合わないブラひもだとか,透明のビニール製のブラひもだとか(何か汗かきそう),ブラの周りの肉だとか,山頂部のシルエットにしても腹のシルエットにしても,ご自身の体型についての配慮があるわけでなし,ともかくそれはセクシーとかいう問題じゃないだろうと思われる姿が散見される。
このように,「セクシーさへの配慮」というよりも,要するに「テキトー」というか「無頓着」な様子が見て取れるのだ。「自由」を愛するパリっ子たち全員がこの糾弾の対象になるわけではもちろんないが,「見せる=魅せる」ということは「見えてもいいや」ということとは違うんだよ,と懇々と説教したくなるような(日本語で),一部の心ない人々が街を闊歩しているのが実相なのである。まあ何割がそうなのかというのはちょっと何とも言えないにせよだ。
▼フランス人のこうした無頓着さは,実は,ファッション以外の領域にもいたるところに見いだせる。近年日本で「最近の女子高生は人前で化粧をする」とか,「ジベタリアンと呼ばれる人種がいて,彼らは地面に座り込んでものを食べている」とかいった報告が,しばしば「旧人類」の驚きと呆れをもって表現されることがあったが,こちらフランスでは「いい大人」ですらそういうことを平気でするのである。私は先日バスに乗っていたときには,座席でアイラインを引いているおばさんから眼が離せなくなった。「揺れたらどうするんだ! おばちゃん,やめとけ!」と心の中で幾度も叫んだが,もちろん当人に聞こえるはずはない。ハラハラドキドキ見ていると,ついに彼女は揺れるバスの中で,何食わぬ顔で首尾よく仕事を成し遂げたのだった。このうえは「ブラボー!」のひとことを心の中で彼女に贈った次第である。ああよかった。
よく考えたら,周知のように日本人は家の中で靴を脱ぐが(もちろん世界的に少数派),こちらの人は脱がない。これもやはり,「ウチ」と「ソト」の境界線を引く場所が違っていることを示している。日本人は靴を脱いで上がれるところ(ウチ)は,自分の身体の延長といった感覚があるからそこには座るし寝ころぶ。逆にソトでは寝ころばない。チョコッと座る人が出てきた程度である。
これに対してフランス人は,まあ印象論なのではあるが,物理的=身体的レベルではウチとソトの境界が曖昧だ。ウチの範囲が圧倒的に小さいとも解釈できる(自分の身体=体表に囲まれた範囲がウチ,もしくはそれよりも小さめ,例えば自分の精神のみがウチ)し,逆に圧倒的に大きいとも解釈できる(どこに寝ころんでもOK。というのは言い過ぎだがどこにでも座りはする)。
これが彼らの衛生観念と関連してくると思われる。多田富雄氏の指摘を待つまでもなく,免疫システムというのは自己と非自己の区別を行うところから出発するものだ。日本人から見れば汚い(=非自己に属する=不快な)ものも,フランス人にとってはそれほどではない。道に犬の糞がたくさん落ちていても,犬がかわいい(=自己に近い=快をもたらす)から許す,というような。
しかし逆に,精神的にはウチとソトはきわめて厳格に線が引かれる。フランス人の友人が,「友達になるってことは,家族になるってことなんだよ」と言ったその言葉が印象的であった。家族および友人はウチ。それ以外はソト。自分にとってウチに属する人とは濃密につきあう一方,ソトに属する人をそう簡単に信用しない。このように人づきあいにおいてはフランス人はかなり保守的であるように見える。蛇足ながら,他方で外国人労働者の権利を擁護する左派リベラルみたいな知識人もうようよいるため,一般人の保守性と知識人の進歩性との齟齬が原因で,問題含みな移民社会ができあがっているようにも見えるわけである(とりあえずいろんな人を入れているが,その反面差別や不公正が日常化しているという意味で)。
▼日本人(主に旧世代)の感覚では,化粧は人前(ソト=パブリックな場所)ではなく,こっそり(ウチ=プライベートな場所)でするものである。なるほどこれは所変われば品変わるイデオロギーにすぎないが,さりとて,日本社会においてはやはり常識という名の文化的基盤の一部にはちがいない。
この,Private/Public という区別も,やはり自己と非自己の境界に関連している。自己は,自身の維持活動(食って,寝ること)を通じて,それ自体プライベートな領域を括りとる。その領域の外側,すなわち自己に属さない領域にあえて自己が「出る」「現れる」ことが,パブリックな場所に立つということである。そのように「私」と「公」を捉え,生物学的次元での自己維持の営みからまろび出つつパブリックな場所にたたずむことこそ,人間の本義たる「活動」(これはすぐれて「政治」的である)と捉えたのがハンナ・アレントという人物であったと私は理解している。
他方,フェミニズムのスローガンに「個人的なものは政治的である」というものがある。が,上述の私の解釈に従えば,これはやや誤解を招くもののように感じられる。これを掲げるフェミニストたちは,好意的に見て「一般には個人的と見られている諸般のことどもを,きっちりと政治的な議論の俎上に載せましょう」と言っているはずであり,単純に「個人的なものと政治的なものの区別などありえない」と言っているのではないはずである。しかしながら,フェミニストの中には後者の解釈(以下,「区別しない主義」と呼ぶ)をとる人々もいるようで,そこは少し違うだろうと突っ込んでおきたい(なお一部のフェミニストはアレントにアクチュアリティーを見いだすけれども,実はアレント自身はけっこう古い考えの人であったと思うのだがいかがか)。
「見せる=魅せる」という仕儀は,自己/非自己の境界を意図的に攪乱するという,人目を惹くに効果的な,しかも主体的な方法のことである。従来なら「見せてはいけな」かった部分をちょっとだけ見せるとか,あるいはもう見せていいことにするとか。そしてその一方で,それをモードの文法の変化という枠組みで「説明」するというやり方。これはなかなか高度な技である。これに対して,「見えてもいいや」というのは,端的に「公私混同」を導くものである。パブリックな場所で,あまりにだらしない格好をしているというのは,「公序良俗」に反するとさえ言えるのである。言いすぎの感もないではないが。
▼なお自己/非自己の境界を攪乱・侵犯する(アラン・ソーカルのニセ論文のタイトルを思い出しますな),ということが,ほとんどつねに「性的」な「快」に接近することであることは強調してもしすぎることはない。性交は(あーあ,ついにこんな話になってもうたぞ),男性にとっては身体の一部が他者の身体に嵌入することだし,女性にとっては体内に異物を招き入れることである。フロイトは,性感帯は身体の「穴」周辺にあると言ったが,それは必ずしも生殖器には限定されない。例えば「食べる」ことは口内に異物(非自己)を入れることだし,「糞便」というのは体内にあるときは紛れもなく異物であるとともに,体外に排出されたあともかつての自己の一部と観念されうる。自分の身体の中に何かが入り込むというファンタジー,もしくは自分の身体の一部が外にとび出てしまう(もしくは切除されてしまう)というファンタジーは,いずれもかなり気持ち悪く,恐ろしく,激しく心を揺さぶる(したがって逆に,快につながりうる)感覚を産み出すだろう。フロイトはこうした体内/体外の敷居のことを「性感帯」と呼んでいるのである。そして逆に,その部位に関わる刺激が,「性的」と呼びうるものなのである(だから,このフロイトの用語は通常の語義よりだいぶ広い範囲をカバーすることになる)。
ところで,どこかで内田樹さんが映画『エイリアン』シリーズはフェミニスト映画だと喝破していたが,その解釈は以下に述べる意味で正しい。すなわちこれらの映画では,内田さんの指摘のとおり,「エイリアンが体内に入り込み,身体を食い破って出てくる」というプロットは妊娠および出産(当然そこに含まれる「性交」も確認しておきたいところ)のメタファーにほかならず,これへの嫌悪がこのシリーズを一貫して流れる通奏低音である。ということは,このシリーズのメインテーマは「性的な快への嫌悪(抑圧)」であるとともに,「性そのものへの嫌悪(抑圧)」であると言えることになろう。つまり,「区別しない主義」的フェミニスト映画,という意味で内田さん的解釈は妥当である。
しかしながら逆説的なことに,この映画がもたらすハラハラドキドキというものは,身体に入ってくるエイリアンの恐ろしさに源泉があるのだろうし,しかももしその恐ろしさがなかったら映画が全く面白くなくなるだろうから,ということは,映画そのものはやっぱり「性的な快」のおかげで成り立っているという(妙ちきりんな)ことになるだろう。言い換えればこの映画は,見ている者がエイリアン(つまり,抽象的に言うと「性」)を嫌悪すると同時にそれに魅了されねばならない映画である。
最終的にエイリアンがやっつけられて,エイリアンと人間の区別もない,何もない,ペンペン草も生えない世界が到来し,映画は幕を閉じる。この最終的な世界は,「涅槃」と呼ばれるものに対応している。「涅槃」は,みながそこを目指す地点だけれども,到達されてしまうと面白くも何ともないホントに何もない世界である。そこでは自己も非自己もない。私も公もない。個人的なものも政治的なものもない。男と女もない(シガニー・ウィーバーのあの頭,「女優」って感じじゃないでしょう)。なーんにもない。
であるからして私は,仮に区別しない主義的フェミニストが「男も女もない世界がいいなー」と考えているのだとしたら,つまり境界そのものがない世界を理想としているのなら,「あなたはそんなペンペン草も生えないような世界を,ホントに理想とするのか?」と小一時間問い詰めたいという立場に立つ者である。
▼これに関連して,今般東京都などで「過激なジェンダー・フリー」への攻撃があるが,これについては私は微妙な立場にいる。私は憎っくき蒙昧派知事の統べる東京都とはまっっっっっっっったく違う意味で,「ジェンダー・フリー」肯定派には与さない人間である。
私がジェンダー・フリー論に賛成できない理由は,「もしそれが実現したら,人間は人間の快をほとんどすべて失ってしまうことになるから」という単純な理屈に由来している。現在2つある性を1つにするということは,とりもなおさず世界を現状より単純にすることである。この単純化で何が失われるかを考えてみれば,これはかなり大きいのがすぐに予想できる。ふつうの意味での性的な快がなくなるだけでなく,恋愛の形も著しく平板になる。現在は,男・女の組み合わせと,男・男,女・女,その他ややこしい組み合わせもいろいろと可能であるが,そういうのは全部なくなるわけだ。しかも男→女という恋愛と女→男という恋愛もきっと質が違うのに,それも消える。そうすると,そういうのに取材した小説,歌,映画,その他諸々の形式をとる芸術すべてが貧困化する。大げさに聞こえるかもしれないが,文化というもの全体が,まるごと,成立の危機に瀕すると言って過言ではないのである(ことほどさように,性ということと芸術ということとは,かくも深く結びついている)。
そんな社会はちょっといただけない。もちろん現在の社会にいろいろ問題はあるだろうけれど,道行く人のブラひもを観察しながらどうとかこうとかくだらないことに思いを馳せられる社会の方が,そんな気すら起きないであろう(他人の着衣などに何の関心も起こらないであろう)公正で平和な社会よりも,私は好ましいと思える。というか,多くの人にとってそうだろうと私は勝手に思う。
▼だいぶ前になるが,エコール・ノルマルにジュディス・バトラーがやってきて講演をした(呼んだのはカトリーヌ・マラブーだろう。今となってはむしろこの人の存在の方が気になるところである)。『ジェンダー・トラブル』のフランス語版が出た記念ということだった(何という遅さだ!)。そこでは案の定ラカン派精神分析に関する質問がいろいろ出された。バトラーはそれらに対し,「私はラカン派だろうと何だろうと,精神分析には与さない。精神分析というものは一般に,主体や家族のあり方を決めてしまう鋳型として機能してしまうものである。そういうのはよくない」と一刀両断だった。
つまらない。精神分析に対するこうした苦言は,もう私は聞き飽きた。だいたいこの人にとって「主体」というのは,生まれつき「自由」をもっている存在,自分というものを思いどおり・自由に構築してゆける存在なのだろうか。そんな主体には「サルトル」とかいう名前でもついているのではないのか。そうではなく,人間生まれ落ちたときから,自分で選べることと選べないことがあるのが当然ではないのだろうか(例えば,人は自分の「性」を選べないだろう。「生」(生まれるか生まれないか)も選べないだろう。「死」は選べた方がいいのかどうか議論中であるがたぶん選べない方がデフォルトである)。
もしも精神分析という発達理論(て言い過ぎだが)がなかったら,そもそも「最初は何でもなかった」人がどうやって(割としっかりした感じの)「主体」となるのかとか,自分の自由とは何なのかとか,その他諸々の事象についてどのように思考すればよいのだろうか。少なくとも精神分析を「既成の社会の鋳型にすぎない」と一蹴するやり方は,そのよろしくない精神分析の対案を出すことに全くならないし,したがって何ら建設的な面をもたない批判のしかたである。「Et alors ?(だからどうした?)」というような。
▼いわゆる「ポストモダニスト」たちや,フーコー派の人々(正確には私はこういう人たちは「似而非」フーコー派だと言いたいけれども。フーコーがそんなバカなはずないでしょ)は,「こんなふうに見えているけれど,実際は違うんですよ」という論法,すなわち「暴露」という論法をつねに,金太郎飴のように,とってきたように思う。例えば「〈男は男らしく,女は女らしく〉っていうのは無根拠なイデオロギーなんですよ」というようにだ。じゃあ,どうすりゃいいのか? そんなイデオロギーはなかったことにしましょう,というのが彼らのお決まりの解決である。彼らにとって「無根拠」というのは「あるべきでない」ことだから,そんなものにしがみつくのは「何かの間違い」なのである。
しかし,そうした「構築された」イデオロギーが無根拠だなんてことは最初から自明であろう。むしろ,例えば「男性性」とか「女性性」といった無根拠な観念が何でか知らないけれど現実にドミナントになっている以上,そんなご無体な現象が何で起こらんとあかんのか,何で無根拠な観念が現実に優位にならざるをえないのか,われわれはその必然性を解読しなければならないのではないか。ここを「偶然」と考えて思考停止するのではなく,さしあたり「必然」と考え,その中身を解読し,その根本原因を究明し,それを取り去るのでなければ,社会から「よろしくない」イデオロギーを本当の意味で取り払うことは金輪際できないだろうに。
しかもである。確かに「暴露」というやり方は,「王様は裸だ!」という宣言としてある程度有効だろう。しかし,けしからんイデオロギーが退場したあとに何をわれわれが構築すべきか(例えば,もっと好ましいイデオロギーをだったりね)については,結局何の教訓ももたらさないのだ。脱構築の脱だけあって構築がない,というのは,やっぱり脱構築ではない。私にとって,バトラーのコメントもそのような種類のものである。
▼そもそも精神分析というものは,自己と非自己の境界線がいかにして立ち上がるのか,という問題を扱いうる,ほとんど唯一と言ってよい理論なのである(もちろん,本質的に内容がかぶっている別分野の理論はある)。だから,精神分析を抜きにして「主体」なる言葉を使うなんてことは,21世紀にもなる今日においてはありえないのである。「主体」は元祖・無根拠なのだから。
という意味で,この分野で精神分析よりも根底的で強力な理論装置があるのならもってきてみろ,とあえて言い放っておこう。たぶんすごい量のお叱りが来るであろう(釣り?)。





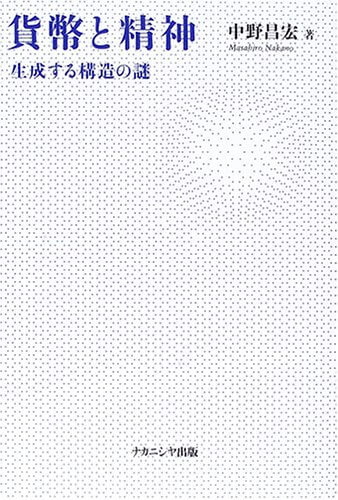
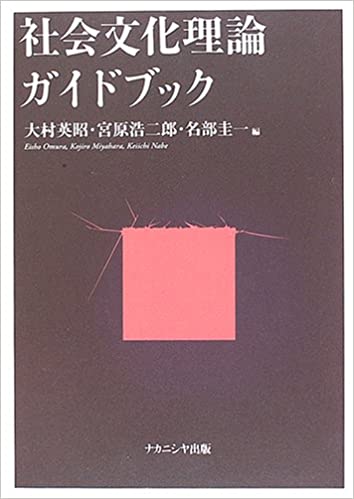




ディスカッション
コメント一覧
えーっと、哲学的なところではなく、ブラひもについてだけなのですが、これが「見せてもよい」ものになったのはフランスでもここ数年のような気がします。ご指摘の「ビニール製」はやはり「本当は見えてはいけないもの」という意識がされている結果ですし(汗はかくかもしれませんが)、一応「いかにも下着ですー」という感じのひもは見せたくないのです。最近のブラは以前の「ストラップレス(つまりひもがはずせるタイプ)から「見えてもいいストラップ付き」に移行しているように感じます。まあ、男性から見れば「ブラひもが見えている」という事実しかとらえられないのかもしれませんが・・・。この傾向が日本にも波及するのかどうか、観察してみたいと思います。
「ブラひも堂々出し」を最初に見たときは私もびっくりしましたが、なれてしまいました。今では日本でも若い子は出しています。ふらんすさんのコメントの通り、真っ白い「いかにも下着」というブラひもが見えていることはまずなく、色つきのものですが。透明ビニールブラひもも登場しています。
最近、ヨーロッパで見てギョッとしたのは、Tバックの下着のひもを見せている人がいたこと。かがんだときに見えちゃったとかいうものではなく、「見えてもいいです」という風でした。いくらなんでもパンツのひも見せるなんて・・・と違和感ありましたが、そのうち日本にも広がるんでしょうか。
nakanoさんの仰る「見えてもいいや」は、私はヨーロッパ女性の白いズボンの下に透けて見える下着の柄に感じていました。日本女性だと(いまのところ)白いズボンを履くときには無地のベージュの下着などを選んではくと思いますが、ヨーロッパ女性は気にしないようで、柄物や黒い下着を身につけていたりしますよね。
ふらんすさん,ビアンカさん,コメントありがとうございました。やっぱりそっちの話題に絞られますよね。当然です。
今日は革命記念日で,シャンゼリゼのパレードを見がてら,皆さんの「ひも」を観察してきましたが(殴)。場所柄フランス人ばかりではなかったわけですね。
ふらんすさん,
「やっぱり見えてはいけないもの」とうっすら意識されているとのご指摘,やはり女性の視点という感じでたいへん参考になります。しかし,ではなぜひもをやっぱり出すことになったのか,疑問は尽きません。可能性として思うのは(1)それが美しい(もしくはオトコの目を引くことができる)からか,(2)それがラクだ(見栄えは二の次という意味で)からか,どちらかだろうと思うのですが。
広告の類にも現れていますが,一般に日本に比べてフランスの性表現はかなりストレートなので,従来見せてはいけないとされていた下着をあえて見せちゃうというやり方=(1)の可能性も捨てがたいのですが,ひもを出さないのと出したのとどっちが美しいのかやはり考えると,やはり何だか(1)ではありえないようにも思うのですが,いかがでしょう。
あと,私個人としては,キャミソールのひもとブラのひもとが交差してたり左右対称になってなかったりすると,見るだけでちょっと気持ちが悪いです。バカですね。
ビアンカさん,
それです! それも書こうと思っていたのに迂闊にも書き忘れました。私もあれは疑問でした。どうして白いパンタロンに色物パンツなのか。そこは見えていいものなのか。あきらかにそこに透けて見えている色と今日の服の色はあっていないような,しかしあっている場合もあったり。と,わざとなのか何なのか,悩んでしまいます。
真面目な女性の方は,「オトコどもは下着が見れてラッキーと喜んでるだろう」と(うすうす)お思いかもしれませんが,この場合それが何だかとりわけ美しいというわけでなく(と私は思いますが),むしろ,わざとやってるのかそうじゃないのか,どういう意味なのか,などと悩んでしまうという。
結局,一種の「だらしな系」じゃないかなというのが私の中の仮説なのですが……。ちなみにウチの家内は太陽アレルギーなので,夏場は肌を出すどころか完全防備です。
日本に波及しますかねぇ。私の予想では,日本人はおそらく焼けることを嫌うと思いますし(ガングロブームはもう去りましたし。あのあと美白ブームはどうなったんでしょうか),したがってフランス人みたいにあそこまで肌を出す服を着る人も少ないと思いますので,「流行らない」ほうに1000点です。
はじめてお邪魔いたします。
ブックマークして時々楽しみに拝見させていただいております。
(先日、勝手にTBさせていただきました。その折はご挨拶せず失礼致しました。)
当方女性ですが、ブラひもに関して、上のGuyさんご指摘の(1)と(2)の融合のような気がします。なぜというなら、フランスではだいぶん前からブラひもをみせていて、それが白くて太くてただのグンゼ(?)ブラのひもでも出していたので、おそらく(2)。その反面、やはりひも無し派もいたようですが減ってきており、代わって黒いキャミソールには黒いブラひも、とオサレにコーディネートする傾向が顕著になってきた点において(1)。
結局、どちらにとっても都合がよい折り合い点なのではないでしょうか。
ローライズジーンズにTバックひも出し、私の聞いたところによると、既に昨年の9月に日本での観察報告がされています。
shibaさんこんにちは。
激しく説得力のあるコメントありがとうございました。そうですね。「どちらか」というわけではないでしょうね。たぶん「どちらも」なのでしょう。
ただいずれにしても,こちらの女性は日本の女性に比べて下着が見えることへの抵抗はかなり少ないように思えたので,考え方というか文化というかの違いとして抽出してみました。
あとshibaさんのコメントから離れて恐縮ですが,「ビニール製ひも」を先日ル・ボン・マルシェ(注・左岸にあるデパート)で確認したのですが,装着者はなんと日本人らしき方でした。目撃現場が免税コーナーでしたので,こちらに住んでおられる方ではないと思われます。背中のひもじゃない部分(ホックのついてる,なんていうんでしょう,横のラインです)まで見えてましたので,ひもだけがビニールであり,ブラ自体はベージュだということがわかりました(そりゃそうか)。出したいけれど見せたくない,複雑な女心を反映していると思いました。
しかし,男性陣からのコメントはなかなかしづらい話題なんでしょうか。そりゃそうかもしれません。一歩間違えば人格疑われそうですからね……。
ご無沙汰してをります。わたくし女性ですから、貴兄が性交なんて言われると顔を赤らめてしまいますの。恥じらってしまふのです。顔が赤らんだついでに、ワイン、フレンチではvinと言いましたか、お口に注ぎ込みましたから顔がかなり赤らみまして、自我も何もないのです。面白き論考故にあたくしも気になるいくつかの点を書かせていただきたいと思います。
所謂、「ミセブラ」なんですが、ワイドショーでかつて取り上げられてをりましたのを見ました。そのとき、何だかなあと言ふ気持ちに至りました。ミセ=見せてもイイ、見えてもイイ、魅せる、そのいずれかだとしてもブラってそう言ふものだったのかしらと思いました。
ヌーブラなんて言ふものもございまして、ヒモなしで特殊な素材でバストがアップしたように見えるやうなのです。ミセがどんどん拡大していくとどこまでいくのでせうか。
ヌーブラだけで歩いていましたら貴兄の言ふところの突起?突起でよろしいのですか?突起の無い状態で歩いているやうに見えます。捕まるのでしょう、きっと。捕まらなくなる時が来てもイイんかいってのは論考に書かれておられたと思うのです。(人類学書なので見かけますトップが見える人に余り何も感じ入らないのはどうしてなんでせうか。)
陰(イン)すれば何とやらと言いますところ、どうなりましょうぞ。
インリンがエロテロリストなんぞと言われまして、普段には絶対にシモネタを話さないなんて言ふことを聞きますと、不思議な気持ちにとらわれるのは自然なことに思われるのです。メディア上ではエロテロリスト、でもノンメディアでは陰。とても良いことだと思われてならないのです。
団鬼六曰く、杉本彩はダメだと。なぜならば、「恥じらい」がないからと言われるのです。(団先生原作の映画化に際して)私もそう思ふのです。「恥じらい」なくて○○なし。
ミセブラ、いきつけばミセ○○、いーんですか?ミセパン、いきつけばミセ○○、ミセ○○○(最低だ(笑))
わたくしもジェンダーフリー教育にはノンでございますわ。もちろん、フロイトを読ませたり、バタイユに迷いを感じたり、日本で語られていた性に関する民話、また落語のバレ噺なんてのは積極的にお子さまにふれていただきたい所存ではございます。(性病の知識と避妊の教育はしっかりする必要があると感じてをります。後は、陰してイイかなと思います。)
最近、精神分析についてわたくしの中で少し迷いがございましたので、この論考にふれまして、やはりウィでいこうと思いました。
男も女もなし。弁別特性として2穴の有/無とか2穴の好/嫌とかそんなんになるのでせうか。それはどうなんでせうか。他にも書き方はありますが、最低なのでやめます。
しかし、「王様は裸だ!」の暴露も裸の王様が屹立した○○○をミセながら「Et alors ?(だからどうした?)」と言われたら、「スンマセン」と謝るしかないのではないでせうか。構築なき脱構築は破壊です。意味ないです。
自己と非自己の境界がなくなるのはアノ時だけでイイです。
根拠だなんだってウルサいわ、まったく。快よ!陰よ!まったく。
ところで「内田樹さんはどこかで」のどこかは『現代思想のパフォーマンス』(光文社新書)です。
上のコメント、ワインのせいか、おかしなことかいてまして、陰すればではなく、秘すればハナのこと言いたかったのです。すみません。
nakanoさん、もしかして透明ひものブラはブラ自体も透明ビニールと思っていらした?「汗かきそう」の真意はそこにあったんですね。
さて、なぜひもを出すことになったかというとやはり答えは(2)でしょう。ストラップレスのブラって一般にあまり快適ではないのです。かといってノーブラはいやですし。で、どうせ出ちゃうならきれいに出そう、ということで服とコーディネートできる色ひもや透明ひもが登場、ということではないかと思います。左右対称でないといらだつ、というお気持ちわかります。でもそこはなんというか、遊び心というか、なりゆきまかせというか・・・。
フランスの下着は日本に比べて体型補正的要素が非常に低く、日本人体型の私など大変こまります。
フランスにはヌーブラ、もしくはそれに類するものはないのでしょうか。
http://www.nubra.jp/
色々な問題が解決すると思うのですが、どうなのでしょうか。
ふらんすさん,こんにちは。
いやいや,ブラ自体が透明ビニールとはさすがに思いません。しかしひも部分だけでも十分,汗で気持ち悪くなるような気がしたのです。
ストラップレスだと快適でないというのは私らにはわからないことで,真面目に教えていただいてうれしいです。
たぁ坊さん(何か勘が狂ってる),
そういう商品があるかどうかはわかりませんが,フランスはあくまで農業国なので,一般に日本市場にみるようなすぐれた工業製品はないのです(中国製でも)。
日本市場というのは閉鎖的とか言われていますが,そうじゃなくて「世界3大難しい市場」なのです(あとの2つは知らない)。クオリティの高いものでないと見向きもされない。ユニクロ的でもなんでも。国民全員がおりがみ折れる器用な人たちですから当然かもしれません。
ヨーロッパの中で工業力が高いのはドイツとかスウェーデンとかでしょうが(詳しく知らない),日本のものに比べれば全然ダメですね。こっちに来る前はもう少しましだろうと予想していたのですが……。オッ,いいものがあるなと思ったら漢字が書いてあって,「Made in Japan」てどっちらけですわ。
実はヴァイオリンをもってきているのですが,そういう職人も日本人の方が腕がいいと聞きます。だから,ちょっと傷んでるところがあるのですがこっちでは修理に出すつもりはありません。
はじめまして。今更ですが、コメントというか、女性側からのちょっとした情報提供をさせて頂きます。
まず、透明のヒモですが、すでに8年ほど前から日本では一般化していると思います。むしろ見えても良いという下着が一般化して、隠すのがもったいないくらいかわいらしいデザインが増えました。また、ヌーブラという吸盤のようなパッドは、米国発のテレビ通販商品だったはずです。当初は9800円もしましたが、今では安価な類似商品が増えました。アメリカンスリーブやキャミソール、ワンショルダーなどの流行と共に普及しました。どちらも、普通のスーパーやドラッグストア等で売られています。このようなアイテムを利用しないと、着られない服が多いんですよね。実際。
チコさん,こんにちは。
情報ありがとうございます。8年前ですか。では私は今までいったい何を見ていたのでしょうか。すっかりご無沙汰,じゃなかったウラシマのような気がします。うちの妻とはそういう服は無縁なせいかな……。
ヌーブラのサイトを私も研究させていただきましたが,おっしゃるようにもとはアメリカの製品を日本の業者が輸入しているようです。アメリカならこういうものを作りそうですね。確かにいかにもテレビショッピングの商品。
ただ,ヨーロッパ人に受けるかというとちょっと無理ではないでしょうか。根拠はありませんが。普通のスーパーで売るなどあり得ないと思えます。何でだろう。
関係ありませんが,10年前パリに来たときに,スーパーに入るなり女性の下着コーナーで,ブラとかガーターベルトが一面に広がる光景に面食らいました。普通1階は食料品,という固定観念を打ち破られた瞬間でありました。
そうそう,それで思い出しましたがフランスではパンストではなくガーターベルトがメインなんですよね。違いますか? それこそ10年以上前留学した友人(女性)がそう断言していましたが。今はどうなのでしょうか。>皆さま
いや……。そんなに深く追求する気はないのですが,こんなところにもカルチャーショックのネタがあるかなと思いまして。
すみません。ホント、酔っぱらいながら読んで、酔っぱらいながら書いて、その後も、関係ないようなことを書いてしまって、申し訳なさでしばらく訪問できませんでした。まったく勘も狂ってるもなにもないです。ごめんなさい。
その後、ちょっと注意して街を歩いていますと、見えるブラヒモの色と服をコーディネートしているなあ、と思わせる人、透明のヒモ、色々おりました。(いつもより気にするようになってしまったのはいかがなものか。)
陳謝でした。
たぁ坊や,(まだやるか)
オイラは別に気にしちゃいねぇぜ。世の中にはいろんな人がいるもんだぜ。いちいち目くじら立ててちゃあな。
皆さんに不快にならない程度にふざけてくんな。(何かぜったい時代劇)
へい、兄さん。(アニさん、です。落語ブームをフランスにも届けるべく・・・)
上方落語は全然聞いていないので、聞いてみたいと思ってやす。何でもそうかもしれやせんが、落語読んでいても、メチエの兄さんのラカンの貨幣論で、噺をただ読んだり、聞いたりするだけじゃない楽しみ方ができやす。まったく理屈とトリモチはどこにでも作っていいやすし、況や落語に理屈なんてゲスの極みですが。(メチエ読んでますってことを遠回しに伝えてみました。ガイドブックは立ち読みで、失礼してます。マルクスは正しい。)
では、失礼。
ジェンダーフリーとは、「公共領域においては_境界_に拘泥しない」立場、とひとまず捉えておけばいいのではないでしょうか? アーレント的公共領域でもハバーマス的公共領域でもいいのですが、公的領域にジェンダーを持ち込むのは、キンダイシミンシャカイとしてはいささかまずいのではないでしょうかね?
相互に境界を侵犯するという豊穣でエロの世界は、私的領域において存分に楽しめばよろしいと私は思うわけです。
で、逆に言えば、公的領域へのジェンダーの持込は、自分好みのエロを公的にさらして、しかも他者にそれを強要することに等しいのではないかと。マジョリティにはそんな権利はないでしょ。
人間はみんなヘンタイ(多型倒錯)なんですから、自分好みのエロを強制してはいけません。
やっぱりジェンダーフリーは正しいのです。
自由からの逃走さん,こんにちは。
お返事遅くなりました。ええと,ジェンダー・フリーは正しいと考える方の多くはフェミニストだと思ったので,公的領域と私的領域との区別を維持するジェンダー・フリーというものに思い至りませんでした。しかしむしろそういう理解が昨今のジェンダー・フリー論の共通見解なのかもしれませんね。そうなのでしょうか。
しかしお言葉についてつらつら考えてみましたが,いろんなことが逆のように思います。
まず「ジェンダー」という言葉自体,生物学的「セックス」に対立されるべく導入された,「社会的に構築された性」というような内容の概念であるはずです。ということはそれは,「社会」というすぐれて「公的」なものがなければ,そもそもありえないはずのものだと思います(「エロ」とおっしゃっているので「セックス」の一語で足りるとお考えなのかもしれませんが)。
また「人間はみんな多形倒錯」という点についてですが,それは基本的にはそうなんですが,むしろ逆に,成長するにつれて「にもかかわらず生物学的セックスに対応するかのような社会的ジェンダーの『標準的』な形(男らしい/女らしい)になぜかハマってしまうのが人間だ」という言い方もできます。子どもは本来多形倒錯だけども,いいとか悪いとかはさておき,現実に,大人になると「標準化」されていくわけです。
実際「ジェンダー」が社会的にのみ構築されるのならば,生物学的性とは無関係に好きなように構築したらいいわけですが,現実はそうなっていませんよね。家の中でも外でも,やっぱり性は性として表現されている。人間はみな,私的領域にとどまらず,公共領域においても性的に標準化されることを強制されている存在です(ということをバシッと言ってのけたからフーコーは尊敬されたのでした)。
で,そういう「標準化」をよくない,とおっしゃる方もおられるでしょうが,そういう方の場合はむしろ,「みんなが倒錯だったら,倒錯のまま育ってしまった大人の人の居場所が増えて,みんなハッピーじゃないか」という議論を展開されます。公的領域での多形倒錯を支持する立場は,つまり,いわゆる性倒錯者の立場擁護に焦点があることが多いです。でもこれって,現実に倒錯的である人の生き方を尊重していることになるのかどうか,私は疑問に思います。
時代の変遷や運動家の尽力で,性についてのみんなの考え方が変わったら,ジェンダー・フリーという理想が実現することもありうるかとは思いますが,そういうことをすることでどれほどの利得が人類全体にとってあるのかが私にはよくわからないのです。ジェンダー・フリーで得られるのは,性倒錯者の方々の心の平安以外に,何かあるのでしょうか。
損失の方は逆にはっきりしていると思います。それ以外の人々の楽しみのほとんど全部がなくなるということです。それは,よいことなのでしょうか。
利得とか損失とか言うと,そういう問題じゃないんだ,正義の問題なんだとおっしゃるかもしれませんが,それはそれできちんとお話を伺わないとなかなか納得しがたい主張だと思います。いかがなものでしょうか。
レスありがとうございます。
>
利得とか損失とか言うと,そういう問題じゃないんだ,正義の問題なんだとおっしゃるかもしれませんが
<
利得と正義を切り離してはなりますまい。両者を切り離すことを是とするのは教条主義というものです。
利得という観点でも、ジェンダーフリーを擁護するべきだと私は考えています。
>
時代の変遷や運動家の尽力で,性についてのみんなの考え方が変わったら,ジェンダー・フリーという理想が実現することもありうるかとは思いますが,そういうことをすることでどれほどの利得が人類全体にとってあるのかが私にはよくわからないのです。ジェンダー・フリーで得られるのは,性倒錯者の方々の心の平安以外に,何かあるのでしょうか。
<
相互安全保障ツールとして、「人権」以上のものを人類は構想しえないのではないかと私は考えています。人類全体にとって、また個々人にとって、相互安全保障は必須です。人権概念を実体化して(つまり聖化して、聖化とは投影ですからね)考えるつもりはありません。ツールとしての有効性が肝要でしょう。
特に私が考慮しているのが、ハバーマスのいう意味での公共領域です。ハバーマスによれば、公共領域とは市民と公権力の対峙する領域ということになります(正確には、私的領域が拡大して公権力と接し、対峙している領域)。個々人にとっては、公権力に対する防衛ラインともいえます。ここが瓦解すると、市民的自由もまた瓦解しますし、人権の深刻な侵害がなされることにもなりましょう。
>
人間はみな,私的領域にとどまらず,公共領域においても性的に標準化されることを強制されている存在です(ということをバシッと言ってのけたからフーコーは尊敬されたのでした)。
<
公領域と私領域の区別そのものはどのような社会にも見られるようですが、その区別のあり方はさまざまです。近代における公私二元論も、近代特有のファンタジー(仮構)という側面はもちろんありましょうし、仮に領域を分割したところで相互に浸透し侵犯するものでしょうね。
ジェンダーの根拠はロールプレイであり世界観なわけですから、「本来は」私的領域に閉じ込めておけるものではありません(セックスの前提としてジェンダーがある、と発言するフェミニストすらいます)。フーコーはいろいろと否定しがたいですよね。
ジェンダーを取り扱うときに問題なのは、それがセックスと現実に切り離すことができず、つまり生殖と切り離せない点にあります。母体が女性というセックスであれば、その精神は「母」たることを要求されるわけです。
ナチスドイツは、「清潔なる帝国」と言われていることはご存知かと思います。
「狭量な民族主義(純血主義)・生殖の管理・倒錯者の抹殺・優生学・・・・」これらはひとつのラインにのっかていますよね。これらが、ドイツの新興プロレタリアの一種の清潔志向からもたらされたものであるといわれています。
>
損失の方は逆にはっきりしていると思います。それ以外の人々の楽しみのほとんど全部がなくなるということです。それは,よいことなのでしょうか。
<
私には、貴兄の発言のここがわからないのです。「それ以外の人々の楽しみのほとんど全部」を具体的にいくつかあげてみていただけませんか?
「マイノリティがでかい顔をすると、マジョリティは不愉快だ」、というのは理解できます。
私自身は、自分でも面白くないと思っているほど性的に「正常」でして、ごくごく正直に言えばある種の性倒錯は個人的に不愉快です。しかし、いくらマジョリティが不愉快だといっても、不愉快という理由でマイノリティが差別されることは容認できません。
と申しますか、マイノリティの権利を擁護することは、マジョリティの権利を擁護することになります。人権とは相互安全保障なのですから。
マイノリティの権利を擁護することが、マジョリティの権利を脅かすことになるという、具体例をともなった立論をしていただきたく思います。
私のいいたいことは、正確には
「公権力と市民が対峙する公共領域において、公権力がジェンダーに拘泥することを許容してはならない」
となります。
これをすこし敷衍して「公権力に限らず、権力(会社の上司とか)がジェンダーに拘泥することを許さない」
までは認められるべきと思います。
そして、現実が猥雑なものになることにはたえなければならないのでしょう。
それが自由民主主義社会における「現実原則」だと信じるしだいです。
敷衍していただいてありがとうございました。なるほど,おっしゃることの正確なところがわかってきました。
確かによく読めば,もともと「ジェンダーに『拘泥しない』」という消極的な表現でしたね。ここに新しく書いていただいたことと総合すると,そういうことなら概ね同意できる考え方だと思いましたよ。
私が想定していた「ジェンダー・フリー」という理念はもっと過激なもので,「拘泥しない」どころか「その存在すら許さない」というほど強硬な考えです。誰がそんなことを言うのかと言われるかもしれませんが,日本社会学会あたりでは実際そういうことを言う人いましたし。
それに比べて自由からの逃走さんのおっしゃることは,暴力的にまとめさせていただくと「政府や会社が男女差別するのはいかん」ということですから,常識的だし,現実原則としてまともな考えだと思います。ただ,そういう考えを「ジェンダー・フリー」とは普通呼ばないんじゃないかとは思いはしますが。
「みんなの楽しみ」ということで私が言いたかったのは,人間が「単為生殖」になったとすると,小説でも映画でも何でも,すごくつまらなくなってしまうだろう,ということです。2つ性があるおかげでいろんな倒錯もむしろ可能になっているわけで,いろんなタイプの性倒錯が現在はありえますよね。が,性が1つになれば(仮定法ですけど)そういうのは全部消えます。
社会的な性であるジェンダーは,一周して生物学的性に回帰してくるように見えはしますが(あるいは「引きずられている」ように見えますが),私の見るところ,結局ジェンダーはセックスには一致できないです。だって結局セックスしかないのなら,性倒錯なんてありえないじゃないですか。一度生物学の次元から,何というか,いわば「離陸」して,そして必要以上にこんがらがってしまうのが,人間性というものの面白いところではないでしょうか。もちろんその裏面にはいろいろな苦しみもあることでしょうが。
ここのところは議論の分かれるところかと思いますが,私のかなり親しくしている友人にゲイがいます。彼は本当に苦難の人生を歩んでいます。しかしながら,その苦難あってこそ,彼の現在の人格がかたちづくられてきたとも言えるわけです(とても真面目な人なのです)。彼のここまでの人生がもっと安閑とした道であったなら,彼もいまこのようになっていたかどうか。まあ仮定の話は意味ないかもしれませんが,要するに,彼が経てきた苦労と,それを通じて彼が培ってきた何かをも含めて,私は彼に尊敬の念をもつのです。
マイノリティーの人権を守るということについても,そんな感じで,相手がゲイであっても何であってもリスペクトできる人はリスペクトするとか,まずはそういう人間関係を自ら築けるということが基本であって,「全員が多形倒錯になれば,マイノリティーもマジョリティーもなくなるし,みんなハッピーじゃん」みたいな発想(こういうのを私は「ジェンダー・フリー」と考えてました)には同調できないと感じるわけです。そういうのは安易だし,逆に観念的ですから。
でですね,私もガイジン暮らしなんで「差別」という問題についてはるる考えるところもあるのです。今度そういうことについても書こうと思っていますので,その節にはまた書き込みなどよろしくお願いしたいと思います。