ダフ屋の経済学
前のエントリーの続き。
たとえば中世イタリア商人の場合を思い起こそう。なかなか東方の文物を自分で買いに行くわけにもいかないので,世の消費者の代わりにこれらを買いに行ってくれるかぎりでは,これは「仲介業者」であろう。他方,子どもが買おうとしているそばから割り込んできて買い占め,子どもたちに高く売りつけようとする輩は「ダフ屋」と呼ばれるのが相当である。
仲介業者であれダフ屋であれ,どうして値をつり上げることが可能なのかというと,財が希少である(その財の生産量が少ない――東方の胡椒にしろ,プラチナチケットにしろ)ために買い占めが可能で,したがって市場を独占ないし寡占状態にできるからである。独占/寡占ができれば,価格は(需要水準の範囲内で)かなり自由に設定できる。誰も欲しくないものであるならばともかく,誰もが欲しいと思うものならば,かなりの高値がつけられる。震災時の便乗値上げ(大根一本1000円……)などを思い起こせばよいだろう。
ということは,こいつらを独占禁止法でしばくことはできないだろうか。あるいは都道府県の迷惑条例,「物価統制令」などが取り締まりの根拠となりうる。まあ, ぜんぜん期待はしていないが。
と思うその観点では,ウィキペディアの「ダフ屋」の項目の記述には,かなり疑問がある。「ダフ屋を取り締まることが独禁法に抵触するかも」云々。これは,一般的な,あるいは専門家の皆さんの見解なのだろうか? だって,ダフ屋が独占を通じて価格をつり上げているのに,それを禁じるはずの独禁法で守られているというのは。そんなのはとても納得できない。
ところで,それだけの価格がつくというのは,ほんとうにその商品にそれだけの価値があるからだ,と考える人もいるだろう。タカラトミーがつけている定価のほうが実は低すぎる評価なのであって,実勢価格こそが真の価格である,と。
これも一つの解釈だ。だがそれは,「価格が適正であるのは,完全競争市場においてのみである」という考え(まあこれも大した考えではないが)とは相いれない解釈である。
どのみち,そもそも近代経済学には「価値」という概念は厳密に言えばないのだから,「正当な」「適正な」価格というものも定義しようがない。価格は需要と供給の「均衡」によってのみ決定されるが,それが正当なものなのかどうかについて,判断する根拠は本来何もない。上にも触れたように,唯一「その価格が完全競争下で決定されたか否か」という点が問題になりそうだが,完全競争という状態自体が絵空事であり,どうせ近似的なところでしか判断はできない。
たとえば「バブル」という語にしても,それは「実体経済」「ファンダメンタルズ」という,厳密には定義できない概念を根拠に言われるにすぎない。「実体経済」を根拠に何かを言う人々は,すべからく経済の実体性を信じていなければならないはずだが,近代経済学者はそれを信じていない(理論の整合性上信じることができない)。だから,「バブル」と発言する権利も本当はない。厳密に言えば,「バブル」と言ってよいのは経済を構成する「価値」に実体があると信ずる者,すなわち労働価値説の立場に立つ者だけである。まああんまり厳密なことは言うと嫌がられるからいいけど。
私個人は,経済学者がどう言おうと,常識的道義的に,製造・流通コストが低いものにものすごく高い価格をつけるべきでないと思うし,子どものおもちゃを投機の対象にすべきでないと思うし,メーカーでも消費者でもない,何も産み出さずただ中間で甘い汁を吸う輩――大人としては大した利益も出ないと思うが――が出るべきでないと思う。
もっと言うならば,実体経済(笑)から離れた金融経済において不生産階級が1日に儲ける金額が,生産階級であるワーキングプアが1月に稼ぐ金額の数百倍もあるというような異常な事態は,あるべきでないと思う。理由は単純で,ある人間の労働が,別の人間の労働の何百倍もの価値があるとはぜんぜん思えないから。どっちも一所懸命に働いてるわけで,それほどの差は個人の能力差には還元できないし。何の差かと言えば,要するに錬金術度(笑)の違いでしょ?
しかし,もともと経済に「べきである/ない」はいっさい通用しないのだ。そこが哀しい現実ではある。






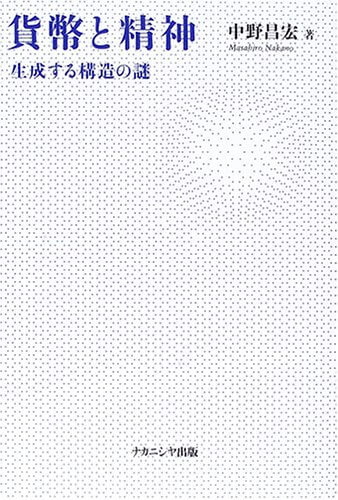
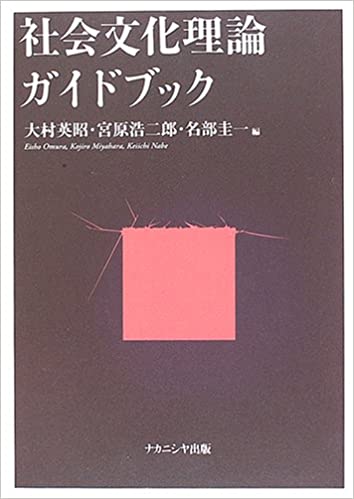




ディスカッション
コメント一覧
概念を厳密に定義していこうとすると、経済用語はほとんど厳密には定義できないのではないでしょうか。実務では「バブル」か「実体」かは相対的な部分もあるでしょうし。
こうなったらおもちゃを買わないとか、父親がおもちゃになるとか。
>しかし,もともと経済に「べきである/ない」はいっさい通用しないのだ。そこが哀しい現実ではある。
中野先生がおっしゃるように、経済はまことに思い通りに行かないものですね。経済学など「競馬の予想屋」ほどの的中率もありませんし…。
しかし、これは「言語ゲーム」ならぬ経済があらかじめ持っている「経済ゲーム」の性質によるものでもあるのでしょう。「もの」を媒介にした交易は「こと」であり、「こと」は実体ではなく現象です。経済もそういった「現象の連鎖」であると考えるならば、非常に「ゲーム性」の高い、不確実な未来を有する「こと」として、ブラウン運動のように振る舞い、中々見極めることは困難です。
精神分析のように、症状として経済をとらえることも不可能ですから、極めて厄介なものであると、つくずく思います。
「ゲーム」の性質をもつものというのは、負けるリスクが常に大きくそれを回避するためには、「ゲーム」に参加しないことが「最大の回避」であるという皮肉から人間は逃れられないということが、私にはいつも腹立たしく思えてしまいます。
けっきょく、「哀しい現実」から我々が逃れることができないという「事実」のみは変わらないのですね。
むむむ、ところでコメントがカウントされなかったのはURLを入力しなかったから?
madhutさん,
ご無沙汰しています。すみません。コメントは最初の1回はモデレートが必要で,次回からはスルーできるようです。どうもそれがWordPressの作法のようですね。
ええと,父親がおもちゃになるのは望むところなのですが,その時間がないのです。特に今年度のこの前期には。新科目が3つも並行して走っているので,もうだめかもです。
木田原さん,
またまたコメントありがとうございます。リンク先を拝見しましたが,ラカニアンでいらっしゃるのですね。話が早い。
> けっきょく、「哀しい現実」から我々が逃れることができないという「事実」のみは変わらないのですね。
そうですよね。実は,経済だってまさに人類の「症状」なんですよ。モノから遊離した言葉の世界(象徴界)がモノ界の疎外態をなすのと同様に,経済システムというのも「生活世界」の疎外態です。ですからその「意味するところ」を「読み取る」ことは一定程度可能なんですが,しかし,人類が疎外から根本的に回復することはたぶん絶対無理でしょうね。
でもまあ,私は根がマルクシアンなので(というか,マルクスの言っているような理想を実現すべく社会のメンバーが努力す「べきだ」と思うので――待っていたら勝手に実現するものでもないので),ある程度明るい未来を夢想して生きようとは思っております。あ,別に活動家とか危険人物ではないつもりですが。
もちろん,経済の「予想」はできませんよ! 経済の先行きを予想できる理論がもし存在したら,パラドックスが生じますので。
> 新科目が3つも並行して走っているので,もうだめかもです。
何をおっしゃるウサギさん。むかし非常勤で講義していたとき、肝心のパソコンを忘れ、仕方がないので落語の真似のようなことをして時間を潰したことがありました。私が学生時代の大学の講義はもっといい加減だったような。
まぁ今は真面目にやらないと駄目なんでしょうね。
> 仕方がないので落語の真似のようなことをして時間を潰したことがありました。
90分まるまる勧進帳というのはきついですよね。「持ちネタ」ができてれば黒板さえあればやれるのですが。
昔の先生なんか,ろくに授業の準備なんかしてないし,トークも板書もひどいし,学生も授業に全く期待してませんでしたよね。質問があれば直接聞きにいけばいいし。自分で図書館に行ったり先生にインタヴューしたり,能動的に動くことこそが勉強でした。
いまは,FD(Faculty Development)といういやな名前のもとに,雛鳥たちに食べやすいように調理して口に入れてやる技術が教員には必要だということになってます。たしかに中にはひどい先生もいるので,ある程度そうかなとも思うのですが,あまりにも過保護で,むしろ雛鳥たちをスポイルしてしまうのにと思います。
>リンク先を拝見しましたが,ラカニアンでいらっしゃるのですね。
いえいえ、私はラカニアンというほどの知識も実績もないですから、ただの「ラカン好き」に過ぎません。
>私は根がマルクシアンなので(というか,マルクスの言っているような理想を実現すべく社会のメンバーが努力す「べきだ」と思うので
頼もしい限りです。中野先生は言うことがはっきりしていらっしゃるので、私も大変尊敬しております。
それから、木田原はペンネームなので、実名をお書きせずに申し訳ありません。日本ラカン協会には入っておりますが、何かとブログでラカン派の方を批判しているもので、こういう名前で通しております。もっとも、私はラカンだけでなく、他の学会にも入っておりますので、ラカンの専門家というわけでもありませんし。
多分、いずれお会いする機会があると思いますので、その時はご挨拶させていただきたいと思います・・・。
時間が経ってちょっと気が抜けちゃいましたが,木田原さん,ありがとうございます。なお,尊敬なんかしないでください。
またどこかでお会いしましょう。
ところで,さっき見たらとあるコマを12,800円で売ってるやつがいた。それはひどいだろう。